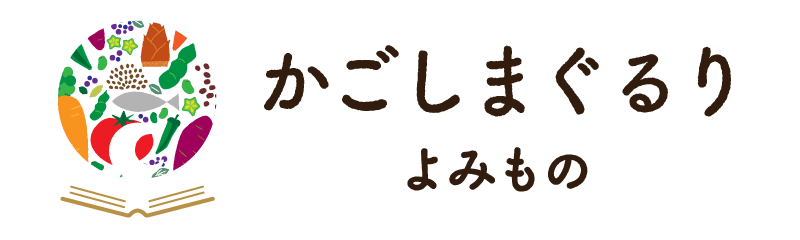「かごしまぐるり」では、鹿児島県産の新鮮な食材や、こだわりの逸品を気軽に「お取り寄せ」していただけます。
詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。
\ 公式サイトはこちら /
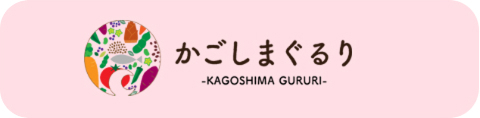
毎年1月7日は、人日の節句の日として、七日正月とも呼ばれており、1年の無病息災を願い、お正月疲れが出始めた胃腸をいたわるため「七草粥」を食べる習慣があります。
皆さんはもう「七草粥」を食べましたか?
七草の種類
昔は、野山で摘んだり、個別に入手することが多かった七草ですが、現代はスーパーで「七草セット」の販売が行われるようになり、何が七草の食材なのかよく知らない方も多いのではないでしょうか?

- せり
若葉が競い合うように生えていることから「セリ」と名付けれました。
鉄分が多く含まれています。 - なずな
“ペンペン草”という別名で知られています。
かつては冬の貴重な野菜とされていました。 - ごぎょう
餅に練り込んで雛祭りに食べるという風習があったことから、雛祭りに飾る人形を表す“形”に“御”をつけて「御形」と名付けれました。 - はこべら
古くから食用として親しまれています。
道端や畑、花壇などあらゆる場所で育つことができる、繁殖力の強い植物です。 - ほとけのざ
ロゼット状に葉が広がるため、仏様の座に見立てて「ホトケノザ」と名付けれました。 - すずな
現在で一般的に食されているカブのことです。
すずなは“菘”や“鈴菜”とも書きます。 - すずしろ
現在で一般的に食されている大根のことです。
すずしろは“清白”と書きます。
「七草祝い」

鹿児島県では、「七草祝い」という地域独自の文化があることをご存知でしたか?
「七草祝い」とは、薩摩藩の時代から伝統的に続いている儀式です。
数え年7才の子どもたちが晴着を着て神社にお詣りした後、親戚やご近所の家など7軒を回って、重箱に七草がゆをもらうという文化があります。
鹿児島県育ちのスタッフは、小さい頃当たり前に行っていたイベントだったので鹿児島だけの文化と聞いて大変驚きました!私の周りでは七五三より七草祝いの方が盛大なイベントのイメージでした….。
最近は、ご近所付き合いが減少していることもあり、親族だけで会食を開いたり、神社によっては七草粥の授与があるそうです。
七草粥の作り方

【朝食にもオススメ!七草粥の作り方】
[材料]
・米 1/2合
・水 炊飯器のお粥の線まで
・塩 少々
・七草
せり 3g
なずな 3g
ごぎょう 3g
はこべら 3g
ほとけのざ 3g
すずな 1株
すずしろ 1本
[準備]
七草の根元はそれぞれ切り落としておきます。
❶米を研いで、水気を切ります。
❷すずなとすずしろは葉と白い部分に分け、白い部分は皮付きのまま2mm幅のいちょう切りにします。
残りの七草とすずなとすずしろの葉は1cm幅のみじん切りにします。
❸①を炊飯器に入れ、お粥0.5合の線まで水を加えます。お粥モードで炊飯します。
❹炊き上がったら②、塩を入れ、全体をよく混ぜ合わせます。蓋をして10分程蒸らしたら完成♪
七草は、米と一緒に炊かない方が雑味や苦味が出にくくなります!
今年の1月7日は過ぎてしまいましたが、この機会に是非試してみてくださいね!
かごしまぐるりでは鹿児島が誇る旬の食材や、加工品
工芸品から観葉植物など様々なものを取り揃えております!
ぜひ一度お立ち寄りください♪
もっと鹿児島のことを知りたい方は!