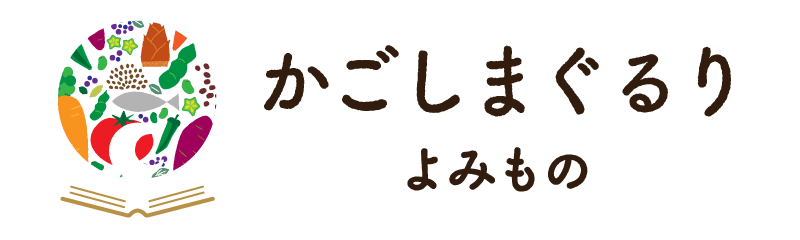鹿児島のほっこりとした味わいが詰まった郷土菓子「あくまき」。
灰汁巻きと書いて「あくまき」と読みます。
鹿児島では有名な菓子ですが全国的にはあまり知られていないあくまきの
歴史や文化、味わいをご紹介!
詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。
\ 公式サイトはこちら /
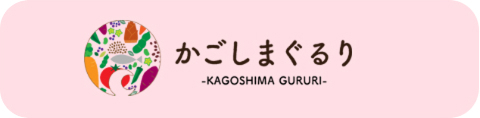
「あくまき」は餅菓子
もち米を一晩灰汁(あく)に浸けておき、同様に孟宗竹の皮も灰汁または水に一晩浸けます。
次に、もち米を孟宗竹の皮で包み、麻糸や孟宗竹の皮を割いて作った紐でしっかりと縛る。
最後に、灰汁で約3時間煮ることで、あくまきが出来上がります。
鹿児島県の風土とあくまきの関係
鹿児島県は温暖な気候と豊かな自然に恵まれており、保存食や郷土料理が多く発達しました。あくまきもそのひとつ。
竹の皮や木灰など、身近な自然素材を活用した製法には、昔ながらの知恵と工夫が詰まっています。

あくまきの味や食べ方は
あくまきの食感はもっちりしており、味はほぼ無味ではありますが灰汁の独特な香りがします。
一般的には砂糖と少量の塩を混ぜたきな粉、白砂糖や三温糖、黒砂糖の粉、黒蜜、砂糖醤油などを好みに応じてかけて食べます。また、蜂蜜、溜まり醤油、わさび醤油、ココアパウダーと砂糖などで食べる人もいます。
たっぷりの砂糖やきな粉と一緒に食べると、独特の美味しさに変わります。
最近では、チョコソースやアイスクリームと合わせて、和スイーツとしてアレンジする楽しみ方も人気。もちもち食感とほのかな香ばしさが、洋風の甘味とも相性抜群です。

通常は常温で食べますが、冷やしても美味しく、固くなった場合は、軽く温めると柔らかくなります。切る際には包丁ではなく糸が使用されます。
大きな刃物の表面積では、柔らかすぎて付着し切りにくいためです。
糸を少し湿らせて、あくまきを一周巻いた後、縛るように引くと、刃物で切るよりも綺麗に切ることができます。

皮で包むときに縛った糸は切り分けに使えます。
鹿児島名物を食べてみよう!

鹿児島の郷土菓子「あくまき」は、こどもの日(5月5日)に食べる伝統の味。
もち米を灰汁(あく)で炊き上げることで、ほんのり琥珀色で独特のもちもち食感に仕上がります。
きなこや黒糖をまぶして味わえば、素朴でどこか懐かしい美味しさが広がります。
「かごしまぐるり」では、そんな鹿児島の伝統菓子・あくまきをお取り寄せで楽しめます。
詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。
\ 公式サイトはこちら /
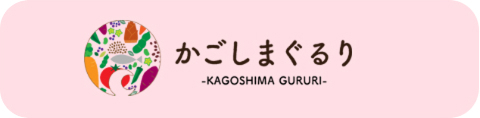
あくまきは保存が効く携行食
あくまきの歴史は、江戸時代まで遡ることができます。鹿児島県はかつて薩摩藩と呼ばれ、独自の文化を持ちました。
あくまきは、この地域の人々に親しまれる和菓子として、その歴史と文化に深く根ざしています。
薩摩藩時代には、あくまきが家庭料理やお祝い事、季節の行事などで作られることが多く、地域の人々の暮らしに密着していました。また、保存性が高いことから、旅行の携行食としても利用されていました。
江戸時代の鹿児島では、薩摩藩が砂糖の生産を奨励していたため、あくまきにも砂糖が用いられるようになりました。特に黒砂糖は、薩摩地方の名産品であり、あくまきの風味を引き立てる重要な要素となっています。

鹿児島県の郷土菓子、あくまきはその独特の風味と食感で多くの人々に愛されています。江戸時代から受け継がれる伝統を今でも楽しめるあくまきを、ぜひ一度味わってみてください!
かごしまぐるりでも美味しいあくまきを販売しています!
どちらも3本、5本入りを選べます。
竹皮が破れただけの訳あり 3本も販売中!



お土産にもピッタリ!
かごしまぐるりの「お土産特集」でも紹介しています。
あくまき以外にもお土産にぴったりの逸品がたくさんありますので、
ぜひご覧くださいませ。
もっと鹿児島のことを知るなら!